
労働者を雇った後に想定していなかったもめごとを抱え、頭を悩ましている経営者の方も多くいるのではないでしょうか。その原因の多くは、雇用者と労働者の労働契約内容に対する齟齬にあります。
この記事では、ドライバーを雇う際に知っておきたい注意点として、契約内容には制限がかけられること及び、雇用契約から当然に発生する権利義務等を民法との関係をふまえて解説しています。読んでいただければ、採用後に発生する「聞いてなかったよ」「そんなつもりじゃなかった」などの問題発生を抑えることができます。
民法と労働法の関係
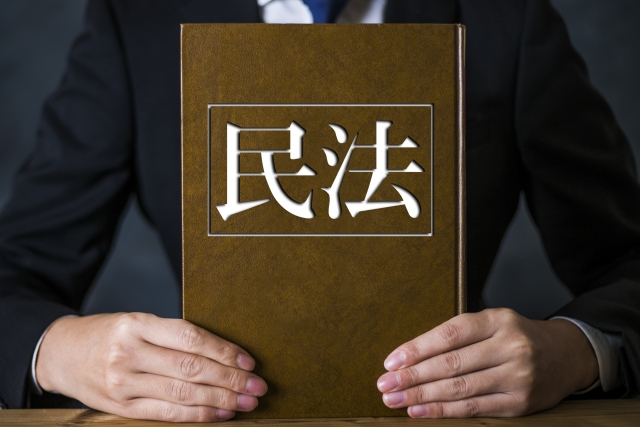
私人間の契約については民法の規定が適用されますが、雇用契約は雇用者と労働者の力関係が大きく乖離しているため、特別法である労働法を設け力関係の均衡を図っています。
労働法は一般法である民法の特別法
一般法とは、広範囲にわたって適用される一般的な法律であり、特別法は、ある特定の分野や事項に特化した法律のことを指します。
民法は、日本の法律制度における中心的な法律の一つであり、私人間や商人間等の関係について規定しており、契約の締結や履行、財産権の取得や移転、相続などに関する一般的な規定がこれに当たります。
一方、労働法は、労働者と雇用者の間の労働関係について規定しており、労働契約の締結や解除、労働時間や賃金、労働条件や労働安全衛生などに関して規定しています。
労働法は、民法とは異なり労働者と雇用者の間の特定の関係に対する法律であるため、特別法の一つであり民法の一部を補完する役割を持ちますが、民法が規定する一般的な規則とは異なる特別な規定も含まれるため労働法が優先して適用されることになります。
例えば、民法521条で定められている契約自由の原則も特別法である労働法との関係で修正を受けます。
契約自由の原則の修正

契約自由の原則とは、当事者間で結ばれた契約に対しては、国家は干渉せず、その内容を尊重しなければならないという原則を言います。
契約自由の原則は、一般的には個人間の契約に関する法的原則であり、当事者が自由に契約を締結することができるというものです。しかし、雇用契約においては、労働者の社会的な弱さが考慮され、契約自由の原則に一定の制限が設けられています。
例えば、労働者が必要な生活資金を得るためには、自らに不利な内容でも雇用契約を結ばざるを得ない場合があります。このような状況では、契約自由の原則が労働者の権利を保護するために制限されることがあります。
具体的には、最低賃金や最低休暇日数などは労働法によって最低限の労働条件が設定され、契約自由の原則を制限しています。
雇用契約から当然に発生する権利義務規範

労働法等の法令による規定がなくても、雇用契約を結ぶことにより下記のような民法上の規範・権利・義務が発生し、民法の趣旨から契約内容の正当性が判断されます。
- 信義則
- 公序良俗
- 人事権
信義則
信義則とは民法の基本原則で「権利や義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない」(法1条2項)と規定しており、相手を裏切ったり、不誠実な対応をしないようにと定めています。
長年同じ顧客を担当しているドライバーは、その顧客と深い信頼関係を築いていたりします。急なコース変更や職務変更を行ったりすると、ドライバーの信頼を裏切ることになるので注意が必要です。また、顧客の信頼を失い事業運営にマイナスになることは言うまでもありません。
公序良俗
公序良俗とは公の秩序又は善良の風俗の略で、民法では「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする」(法90条)と定められています。
例えば、規則に「社員が会社に対して不利益になる情報を持っている場合には、その情報を開示してはならない」という禁止条項を盛り込んでいたとしても、「労働者が法的義務を履行することを妨げるような条項は、公序良俗に反する」と判断し、労働契約が無効となります。(最高裁平成26年2月11日判決)
人事権
人事権とは一般的に、労働者の採用・配置・昇格・昇給・移動・懲罰等を行う権利をいい、これを直接定めた法令はありませんが、契約上当然に発生する権利として使用者に認められています。しかしこの権利も無制限に認められるものではありません。
権利濫用法理による制限

民法では「権利の乱用は、これを許さない」(法1条3項)と定めており、労働契約法でも「労働者及び使用者は、労働契約に関する権利行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない」(法3条5項)と定めています。
これは一般的に権利の行使と言えるようなものでも、それによってもたらされる結果が妥当でない場合は権利行使を認めるべきでないという法理で、転勤や解雇の際に問題となることが多くあり適正な手続きを踏む必要があります。
人事権を適法に行使する為の手続きとは
人事権を適法に行うためには、「労働契約上の根拠のを示すこと」「権利濫用ではないこと」が必要になります。運送業では出勤時間の変更が多々あると思われますので、昼勤から夜勤へ変更する場合を考えてみましょう。
労働契約上の根拠を示すこと
就業規則には絶対的記載事項として「労働日における始業と就業の時刻」の記載が必要ですが、ここに夜勤の時間が記載されている必要がります。さらに、労働者個別の労働契約書に「業務の都合により夜勤への変更もある」との記載が必要です。
権利濫用ではないこと
出勤時間の変更によって労働者が著しい不利益を被る場合、その変更は無効になる可能性があります。個別の判断は難しいのですが、老親の介護が必要な場合などは濫用に該当する場合があるでしょう。
法令の理解は複雑、専門家も活用しよう
このように、使用者の権利・義務に関しては法律に明示されている分かりやすいものから、明文化されていないものの契約上発生するものがあります。中には判例を読み解かなかなければならないものがあるため、素人の判断では後々遺恨を残す場合があります。自分にとっての都合の良い解釈を行い不都合な結果を生み出さないよう、専門家に相談することをお勧めします。
この投稿へのトラックバック
トラックバックはありません。
- トラックバック URL
この投稿へのコメント