
運送業を営むためには行政機関から営業許可を受ける必要があることはご存知の方も多いでしょう。
しかし行政機関との関わりはは許可申請時だけではなく、営業許可を受けた後も必要になります。大きな事故を起こした時だけでなく普段から求められるコンプライアンスがあり、違反があれば処分の対象です。
ここでは運送業を営む方向けに、普段からどういったことに注意すべきなのかを代表的なものにつきまとめます。また万が一違反してしまった場合のリスクについても知っておきましょう。
トラック運送業は、トラック運行状況・管理方法についての法令違反がなされていないかを取り締まる為に、大きく次の2つの行政機関から行政指導、取り締まりを受けます。
1⃣地方運輸局(適正化事業実施機関)
2⃣労働基準監督署
この行政指導、取り締まりの結果いかんによっては事業を継続することが困難になります。
それぞれの行政機関の具体的な監査の方法、違反の確認項目、どのような処分がなされるのかをこの記事にてご確認ください。
地方運輸局(適正化事業実施機関)の監査と処分

トラック運送業を運営するには国土交通大臣の許可が必要(貨物自動車運送事業法3条)で、同法により定められているルールを守られているか確認があります。
それが適正化事業実施機関が行う巡回指導と地方運輸局による監査です。
これら2つの違いを確認しましょう。
適正化事業実施機関による巡回指導とは
トラック運送業に対する適正化事業実施機関による巡回指導は、各地方自治体のトラック協会により行われ、指導の対象となる内容は次のものが挙げられます。
|
・運行ルートの適正化 ・運行計画の見直し ・車両の点検整備 ・安全運転の徹底など |
指導は、事前のヒアリングや調査に基づき、業者ごとに適切なアドバイスが提供され、運送業者が業務改善に取り組むことで、運送サービスの質の向上や、交通事故の減少などを目的としています。
この巡回指導によって営業停止等の行政処分を受けることはありませんが、指導によって問題が改善しない場合や法令違反がある場合は、地方運輸局による監査が行われます。
つまり監査より前に巡回指導というのが一般的な順番です。
地方運輸局長が行う監査とは
監査とは、行政機関が法令遵守や業務遂行の適正性を確認するために、対象の事業者や団体に対して調査や検査を行うことを指し、法令違反や不正行為の有無を調査し、その結果に基づいて問題点を指摘し、違反行為を是正するように指示を行うことを言います。
地方運輸局の監査は主に次の項目です。
|
・運送業者の許可証の発行や更新 ・運行状況の確認 ・運送車両や運転手による点検 ・運送物品の安全性の確認など |
監査は総じてトラック運送業者が適切に運行されていることの確認が目的で、必要に応じて指導や指示を行います。
監査により、道路交通法や関連する法令に違反していることが発覚した場合は、地方運輸局は行政処分を行うことができ、車両使用停止、事業停止、許可取消の3種類があります。車両使用停止は一定期間トラックの使用ができなくなり、事業停止は一定期間運送業を行うことがでず、許可取消は運送業許可が剥奪されます。
地方運輸局による監査が行われると、何某かの行政処分が行われる可能性が高いので、巡回指導の内に改善を行い、監査が行われないように専門の要員を備え、日ごろから管理を徹底しておくことが必要です。
| 主体 | 行動 | 内容 |
|
適正化実施機関 |
巡回指導 | ・監査に先立ち行われる ・ヒアリングに基づくアドバイスがメイン ・落ち着いてアドバイスを受け入れる姿勢が大事 ・指導に従わないと監査に移行する |
| 地方運輸局 | 監査 | ・法令上の問題点を指摘 ・是正するように指示、指導 ・違反内容によっては行政処分の対象 |
労働基準監督署の調査と行政処分とは
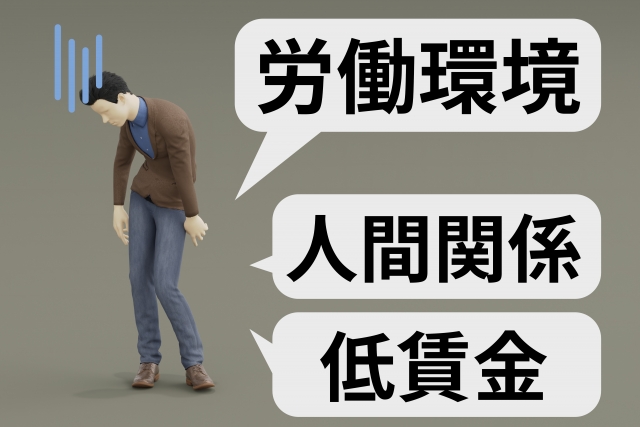
労働基準監督署の調査は、労働基準法に違反している行為が行われていないかを確認するもので、労働時間や休憩時間、賃金などの労働条件が適切か、健康と安全な労働環境が整備されているかなど、労働者の権利や安全な労働環境を確保することを目的として行われます。
調査は定期監督と臨検に分かれ、調査の結果、違反が発見された場合は、労働基準監督署は適切な措置を講じることができます。
労働基準監督署による定期監督とは
定期監督とは、労働基準監督署が定期的に行う労働基準法の遵守状況の現地調査のことを指し、労働者の権利や健康な労働環境の確保のために、労働基準法が適切に遵守されているかどうかの確認を行います。
労働基準監督署の臨検とは
臨検は、労働基準監督署の調査員が現場に訪れ、労働条件や労働環境を確認することで行われます。臨検は、定期的な定期監督とは違い、例えば労働者からの苦情や報告などがあった場合に行われます。
労働基準監督署は、違反の程度や状況に応じて、是正勧告や命令に加えて、違反行為に対する罰則を科すこともあり、例えば、改善勧告に従わない場合には、罰則金を課すことがあります。
また、違反が重大な場合には、刑事事件として処理されることもある為、適宜専門家に相談する方ことをお勧めいたします。
| 行動 | 内容 |
| 定期監督 | ・定期的に行う労働基準法の遵守状況の現地調査 |
| 臨検 | ・労働者からの苦情や報告があった場合に行う ・是正するように指示、指導 ・違反内容によっては行政処分の対象 |
この記事のまとめ
トラック運送事業者が知っておくべき行政機関による処分主体は大きく2つです。
運送業務のコンプライアンスチェックを目的とした適正化実施機関及び地方運輸局長並びに労働法関連の法令違反確認を目的とした定期監督及び臨検ですね。
いずれも、まずはアドバイスを目的とした確認があり、その調査結果、是正態度に応じて大きな処分に繋がるリスクが生じます。普段のコンプライアンスが不安な事業者は事前に専門家にご相談されることをオススメします。
この投稿へのトラックバック
トラックバックはありません。
- トラックバック URL
この投稿へのコメント