
近年行政からの指導・監査が厳しくなってきており、関係法令およびコンプライアンスの順守は事業の継続に不可欠になってきています。
運送業に関連する法令は別表のように多岐にわたっており全てを完全に理解するのは困難です。人員に余力のある大企業は別として、法律知識に明るい総務担当者を専任として対応させることも難しいのでは無いでしょうか。
とはいえ法律について全く理解していないのは問題です。
この記事では最低限は知っておくべき法律について言及します。
トラック運送業経営者が押さえておくべき法令
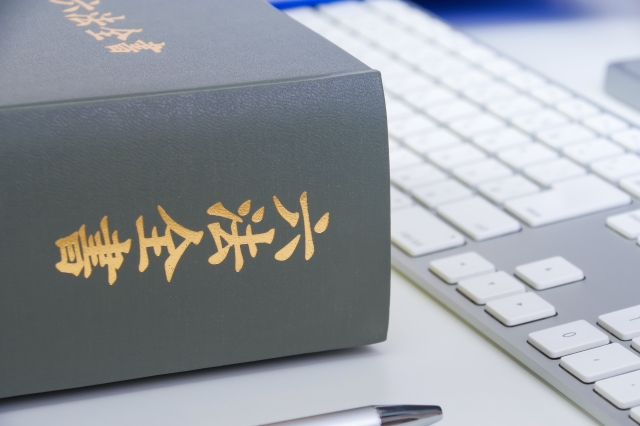
トラック運送業経営者が抑えておくべき法令として大きく3つあげられます。
1⃣運送業特有の「貨物自動車運送事業法関係」
2⃣商取引に関する「民法・商法関係」
3⃣労働者を使用する際の基準となる「労働法関係」
それぞれ確認しましょう。
1⃣運送業特有の主な法令
| 法令 | 内容 |
| 貨物自動車運送事業法 | 運送業の運営に関する法律 |
| 道路運送車両法 | 車両の保安基準・整備・点検等に関する法律 |
| 道路交通法 | 免許制度や道路の使用方法等に関する法律 |
2⃣商取引に関する主な法令
| 法令 | 内容 |
| 民法 | 債務不履行・損害賠償など私人間の権利義務についての法律 |
| 商法 | 商人間の取引についての法律、民法に優先して適用される |
| 会社法 | 会社の種類・設立・運営・管理・清算などを定めた法律 |
| 下請け法 | 下請け代金の支払い遅延防止など下請け会社の保護を目的とした法律 |
3⃣労働に関する主な法令
| 法令 | 内容 |
| 労働基準法 | 賃金・労働時間・休日・就業規則等労働条件の最低基準を定めた法律 |
| 労働安全衛生法 | 労働者の安全と健康を確保することを目的とする法律 |
| 労働者災害補償保険法 | 業務災害、通勤災害等について定めた法律 |
| 雇用保険法 | 失業給付等雇用保険の手続き等を定めた法律 |
| 労働契約法 | 労働者の定義や労働契約の基本条項を定めた法律 |
全ての法律を網羅的に理解できているのが望ましいのですが、経営者は経営のプロであり法知識獲得のために多大な時間を割くのは筋が良くないと思われます。
とはいえ1⃣の運送業法では日常点呼など日々の業務に深く関連する「貨物自動車運送事業法関係」で定められているので細かいものまで理解する必要があります。
しかし「商取引に関する法律」・「労働に関する法律」に関しては一通りの内容を理解したら、いざ関係がありそうなことが起きたら専門家の力を借りる方がいいかもしれません。
よってこの記事では最低限知っておくべき法律としてトラック運送業特有の「貨物自動車運送事業法」関連及び近年残業規制等でがとりあげられている「労働に関する法律」について解説します。
貨物自動車運送事業法関係
「貨物自動車運送事業法」に関連する法令は、日々の業務に直接かかわってくるためその内容を深く理解する必要があります。
特に「貨物自動車運送事業輸送安全規則」は、労務管理に関する事項・運行管理者・整備管理者等の選任・点呼執行方法・各台帳の管理方法等、トラック運送業務において日々必要となる事柄が網羅されているためできる限り深く理解する必要があり、また弁護士・社会保険労務士等の士業でもこれらの業務に精通した専門家が少ないことからなおさら勉強が必要です。
運行管理者試験は知識の整理に役立つ
ではどうすれば網羅的に勉強出来るのでしょうか。
勉強法としては「運行管理者資格試験」を毎年受験することをおススメします。運行管理者試験は下記のように関係法令が網羅的に出題されます。
- 貨物自動車運送事業法
- 道路運送法
- 道路運送車両法
- 道路交通法
- 労働基準法
もうすでにお持ちの方も多いかと思いますが、資格取得時点の知識はだんだん薄れてくるうえ、毎年のように法改正が行われます。知識のブラッシュアップを図るうえでもおすすめの勉強法です。
労働に関連する法令関係
「労働法」に関連する法律は必要最小限の事項を抑えて専門家と顧問契約を結び、経営者の負担を減少させることが望ましでしょう。
顧問契約の必要性
経営者は会社という組織がある為に、立場の弱い個人である労働者に対して無意識的ながらも無理な労働条件で働かせていることがあり、ほとんどの労働者は使用者から支払われる賃金のみで生活しているため、使用者に逆らうことができず劣悪な環境で働き続けることになります。労働関係法は使用者労働者の力関係を調整し、より良い職場を作ることを目的としています。
労働関係法についても深い知識があるに越したことがありませんが、立場の強い使用者は独善的な解釈を行いがちで、気が付けばブラック企業になっていたということもある為、労働関係をまとめた簡単な書籍を1冊読み終えたら、いつでも専門家に相談できるように社会保険労務士と顧問契約を結んでおくことをおすすめします。
顧問契約は税理士だけという方がほとんどだと思いますが、労働審判の件数が3,907件(最高裁判所事務総局による令和2年司法統計)と制度創設以来増加し続けていることを考えると、労働問題で裁判沙汰にならないよう顧問契約の必要性は増しているといえるでしょう。
しかし任せきりになるのもよくないので、ハローワークや労働基準監督署が主催しているセミナーに参加して知識をブラッシュアップすることも必要です。
この投稿へのトラックバック
トラックバックはありません。
- トラックバック URL
この投稿へのコメント