
近年、労働環境にに対する規制が強化される中、より安全で持続可能な運送を目指す動きが広がっています。
運送業においてもトラックの事故防止やドライバーの労働環境の改善に向けた法律改正が進められています。
かつては参入規制が厳しく新規参入が難しかった
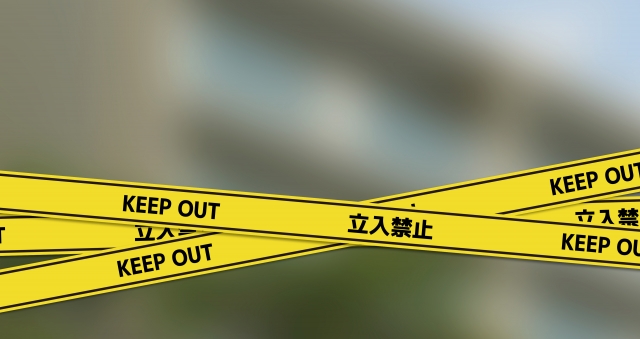
もちろんこの規定にもトラックは公道を走る凶器の側面があることから、過当競争よってもたらされる過重労働による事故で、国民が害されないようにするという目的があったのでしょう。
そのほかにも、「有蓋車庫要件」「最低保有台数」が現在より厳しく設定されていたこと等があり、小規模資本で新規参入することは非常に難しい状態でした。
この参入障壁の高さ故か、資本力のある大手運送会社が全国展開していくのもこの時期と重なり、現在でもその地位はゆるぎないものになっています。
規制緩和と小規模トラック事業者の激増

このような強度の規制の下では新規参入がままならず、高度経済成長に伴う物流量の増加や、新たな輸送方法に対するニーズに答えられない状況が続いていました。
新規参入業者が増えたことにより、地区ごとの共同配送や商業施設内の館内配送業務、路線便の共同運行等新しいサービスが増えます。その反面、競業会社が増加したことによりサービス競争が激化し、長時間の荷待ちや商品の棚入れ、荷物の遅れに対する無償輸送、貨物事故に対する高額な弁金の支払が常態化するようになりました。
運賃が「認可制」から「届出制」へと変更

行き過ぎた規制緩和に対する再度の締め付け

このように、規制緩和によりトラック輸送業界は運送業者の飽和による過剰サービス、低賃金、長時間労働、ドライバー不足に悩まされるようになりました。
行政はこれまでトラック運送業者に対し「Gマーク」取得に対する監査等、監査を受けることによるメリットを享受するための監査がメインとなっており、労働時間管理や安全教育等の監査を行うことはまれでした。労働基準監督署の監査でさえ、トラックターミナル内の会社に対しては行われないという眉唾な話まで出るくらいです。
これに対し、国土交通省では平成25年9月の公示でに自動車運送業の監査方針、行政処分の見直しを行っています。今後は運行管理者・整備管理者の未選任や点呼の未執行等輸送の安全確保が不十分な業者に対し、厳格な処分が予想されています。加えて2024年問題(全日本トラック協会資料より)として取り上げられるように、トラックドライバーの労働時間管理にも本腰を入れており労働環境の改善にも本腰を入れていると強く予想されます。
この投稿へのトラックバック
トラックバックはありません。
- トラックバック URL
この投稿へのコメント