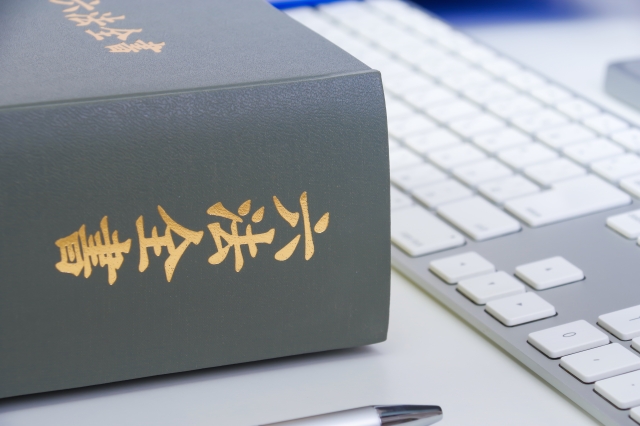
労働者との雇用契約は労働法によって制限されていることはご存じでしょう。
しかし、その労働法がそもそも何に準拠して何のために制定されているかまでは理解されている方はそう多くないと主負います。もちろん、そこまで知らなくても会社を経営するうえで、大きな問題になることはありません。しかし、「労働法に反していないから大丈夫」「法律の範囲では何をしてもOK」という考えでは知らず知らずのうちに労働者に見限られてしまいます。
労働法が何に準拠し何のために定められていることを知ることで、労働者との良好な関係を築くことができ、労働問題を未然に防ぐことができるようになります。
この記事では、労働法と憲法の関係について解説しています。労働問題を未然に防止するのきっかけになりますので参考にしてください。
憲法と労働法の関係
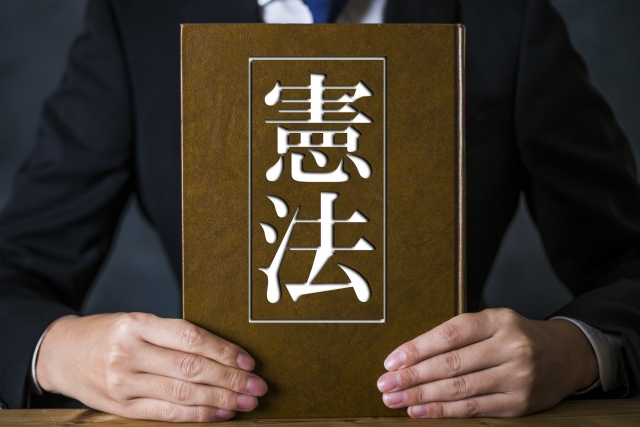
日常の労務管理をするうえでは、労働基準法をはじめとする労働法ばかりが意識され、憲法を意識することはほとんど無いかもしれません。基本的に憲法は「国家からの自由」を定めており、これは国民が国家から制約を受けないことを意味していますが、一方で弱者救済のために強者の権利を制限する「国家による自由」も定めています。労働法は憲法の定める基本的人権が根本にあり、憲法の「国家による自由」を具現化した法律と言えます。
労働者の権利や自由の保障

憲法第25条は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定しています。
この憲法の精神を具現化したものが、労働基準法や最低賃金法であり、労働者の最低賃金や最低休日、労働時間の規制、有給休暇などが定められています。これにより、労働者が劣悪な環境で酷使されることが回避され、健康で文化的な最低限度の生活を送ることができることの根拠となります。
運送業では基本給を安く抑え、職能給・技能給を支払うことによりかろうじて最低賃金を下回らない賃金体系になっている企業が多く見受けられます。法的には問題なくてもこのような賃金体系のままではドライバーに応募してくる労働者は減少し、労度時間規制や有給休暇の取得に悪影響を及ぼし、最終的には事業経営が困難になります。
困難なことではありますが、基本給を上げることは法の趣旨をくみ取るとともに、事業継続の為にも必要なことだと考えます。ドライバーを確保するための手段として優先的に取り組む必要があるでしょう。
社会的安全の保障

憲法第27条は、「すべて国民は、社会的保障の水準を向上させるため、及び文化的生活を営むために、必要な施策を講ずることに努めなければならない」と規定しています。
この憲法の精神を具現化したものが、労働者災害補償保険法や雇用保険法、年金法、健康保険法、介護保険法などの社会保障制度であり、労働者が病気や事故、老後などに備えて保障を受けられるようになっています。これにより、労働者の社会的安全が保障され安心して労働できるようになっています。
しかし、制度が設けられていてもこれを運用できる体制が整っていなければ労働者の不満は逆に高まるものです。例えば、病気や事故で入院した際に提出する「限度額適用認定」が遅れたりすると、たとえ後から戻ってくるとはいえ、一時的な医療費の出費がかさみ労働者からの信用を失いかねません。
これに備えるためには、労務を専門に担当する職員を配置するか、いつでも専門家に相談できるような体制を構築しておくことが望ましいといえます。
労働組合の自由の保障
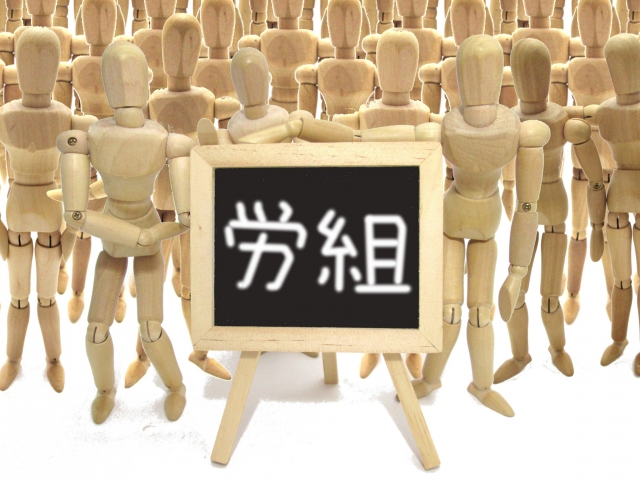
憲法第28条は、「労働組合は、その結成及び活動の自由を有する」と規定しています。この憲法の精神を具体化したものが、労働組合法であり、労働者が自由に労働組合を結成し、集団交渉やストライキを行うことができるようになっています。これにより、労働者は使用者と対等の立場で自己の権利を守り、労働条件の改善を図ることができます。
労働組合というと、経営者側からすると兎角面倒な存在に思われがちですが、ドライバー個々に対応するより組合の意見としてまとめてもらった方が、効率的に問題解決を図ることができるようになります。また、労働組合は相談窓口の役割を果たしてくれるので、いきなり労働基準監督署に駆け込まれるようなことが減り、経営者側にもメリットは大きいものと言えます。
雇用機会の均等
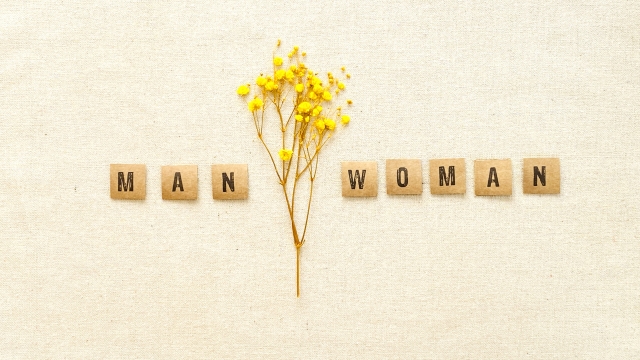
そのほかにも、憲法14条は「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的又は社会的地位において、差別されない」と定めており、この具現化の一例として、男女雇用機会均等法等が定められています。
運送業界全体でトラックドライバーが不足している現状では、女性ドライバーは貴重な戦力となりえる存在です。説明のつかない賃金格差をなくし女性ドライバーが就業しやすくすることで、輸送力の確保を図りましょう。
この記事のまとめ
トラック運送業経営者は、労働法に関する知識を持ち、労働者の権利や自由の保障、社会的安全の保障、労働組合の自由の保障、雇用機会の均等について簡単にでも把握しておきましょう。
労働法と憲法は密接な関係があり、労働者の権利や自由を保障するために制定されています。適切な労働法の遵守によって、労働者と企業の双方にとって公正な労働環境を実現することができます。
とりわけ労働者との関係については、労働法が守られているかだけではなく、その理念も尊重することにより、労働トラブルの起こりにくい雇用関係を築くことができるでしょう。
この投稿へのトラックバック
トラックバックはありません。
- トラックバック URL
この投稿へのコメント